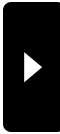2011年06月23日
アガパンサス
近所でみました。
アガパンサスは百合科。原産地は南アフリカです。
ヤサシイエンゲイより引用しました。


アガパンサスは百合科。原産地は南アフリカです。
南アフリカ原産の草花で、野生の種は約10種が知られています。アガパンツスと呼ぶこともありますが、単に属名アルファベット表記「Agapanthus」の読み方違いです。園芸品種は300種以上あり、開花時期や草丈などのバラティーに富んでいます。
冬でも葉が枯れない常緑種と、枯れて休眠する落葉種の2タイプがあります。また、その2つの中をとった性質の種もあり、それらは中間タイプと呼ばれます。地中には茎が肥大して球根のようになった根茎があります。多肉質で水分のたっぷり含んだ太い根をもっています。
地際から光沢のある細長い葉を何枚も出します。その間から花茎を長く伸ばし、先端に数十輪の花を放射状に咲かせます。開花時期は種によって若干異なりますが、梅雨時期を中心として早いものでは初夏、遅いものは夏~秋です。
花色は紫、青紫、白などがあります。紫や青紫色は品種によって濃淡の違いがあり、それなりに色彩のバラエティーはあります。大株では花茎を何本も伸ばし、満開時は賑やかです。
花の形は先端の大きく開いたラッパ型で横向きに咲くものが多いですが、下向きや上向きに花が開くものもあります。草丈は30cmくらいのコンパクトなものから1mを越す大型種まであります。
広くはユリ科とされていますが、分類体系によってはユリ科から分離されたネギ科に分類されたり、さらにさらにそこから独立したムラサキクンシラン(アガパンサス)科とすることもあります。分類的にはあやふやな点の多い植物です。
和名は「ムラサキクンシラン」と言いますが、この名前で呼ばれることはまずありません。クンシランは縁もゆかりもない別属の植物で、外見の特徴から付けられた和名のようです。クンシランに姿が似て紫色の花を咲かせるという意味でしょう。
派手さはないですが、曇天の梅雨空に冴えた色を演出してくれます。
ヤサシイエンゲイより引用しました。


2011年06月19日
アサヒカズラ
大分市の佐野植物公園温室でみました。
アサヒカズラはタデ科。原産地はメキシコです。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

アサヒカズラはタデ科。原産地はメキシコです。
メキシコ原産のつる性の半低木です。非常に生長が早く、温度の十分に確保できる温室内や原産地ではぐんぐんとつるを伸ばしてその長さは10mにも達します。花は一つの花序(花が付いている茎)に十数輪付きその先端がまきひげになっています。その巻きひげを他のものに絡ませて体を支えます。
葉は先のとがったハート形で厚みは薄く、少しシワがよります。きれいなピンク色の花は萼(がく)が色づいたもので、長期間色あせずに楽しむことができます。園芸品種に白花の「アルブム」があります。
開花期は主に夏ですが、気温の高い熱帯地域では季節を問わずに開花します。地中にイモができ、大きくなると5kgもの重量に達します。イモは食用にもなり味はナッツ類に似ているそうです。日本でも沖縄では露地で見事に咲きほこるアサヒカズラを見ることができます。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

Posted by ひろぼう at
11:17
│Comments(0)
2011年06月18日
アリオギネ・ラベンダーガール
我が家の花です。
アリオギネはアオイ科。アリオギネ属。原産地はオーストラリア南西部です。
アリオギネより引用しました。


アリオギネはアオイ科。アリオギネ属。原産地はオーストラリア南西部です。
「ブルーハイビスカス」と呼ばれていますが、ハイビスカスの仲間ではありありません。花がよく似ているところから名づけられたようです。
アリオギネより引用しました。


2011年06月16日
ストケシア
我が家の花です。
ストケシアはキク科。北アメリカ原産です。
ペレニアルガーデンでよく見かける丈夫な花です。ヤグルマギクに似た花弁が細かく分かれる花は繊細な印象ですが、株全体としてみると野性的な雰囲気をもっています。
葉は笹のようなやや細身の形をしており、株はやや横に広がります。
自然と分枝するのでこんもりまとまります。
ストケシアより引用しました。

ストケシアはキク科。北アメリカ原産です。
ペレニアルガーデンでよく見かける丈夫な花です。ヤグルマギクに似た花弁が細かく分かれる花は繊細な印象ですが、株全体としてみると野性的な雰囲気をもっています。
葉は笹のようなやや細身の形をしており、株はやや横に広がります。
自然と分枝するのでこんもりまとまります。
ストケシアより引用しました。

2011年06月15日
ハナショウブ
我が家の花です。昨年は咲きませんでした。今年は咲いてくれて母も喜んでいます。
ハナショウブはアヤメ科、アヤメ属。
Wikipediaより引用しました。

ハナショウブはアヤメ科、アヤメ属。
ハナショウブはノハナショウブ(学名I. ensata var. spontanea)の園芸種である。6月ごろに花を咲かせる。花の色は、白、ピンク、紫、青、黄など多数あり、絞りや覆輪などとの組み合わせを含めると5,000種類あるといわれている。大別すると、江戸系、伊勢系、肥後系の3系統に分類でき、古典園芸植物でもあるが、昨今の改良で系統色が薄まっている。他にも原種の特徴を強く残す山形県長井市で伝えられてきた長井古種や、海外、特にアメリカでも育種が進んでいる外国系がある。
近年の考察では、おそらく東北地方でノハナショウブの色変わり種が選抜され、戦国時代か江戸時代はじめまでに栽培品種化したものとされている。これが江戸に持ち込まれ、後の三系統につながった。長井古種は、江戸に持ち込まれる以前の原形を留めたものと考えられている。
一般的にショウブというと、ハナショウブを指すことが多い。
Wikipediaより引用しました。

2011年06月12日
名前が分かりません
くじゅう花公園でみました。きれいな花でしたが、光が強くてあまり写りが良くありません。
何方か名前が分かる方は情報をお願いします。(_ _)



名前が分かりました。1,3枚目はネメシア、2枚目はデルフィニュームです。
何方か名前が分かる方は情報をお願いします。(_ _)



名前が分かりました。1,3枚目はネメシア、2枚目はデルフィニュームです。
2011年06月09日
お花畑
くじゅう花公園でみました。ポピーのお花畑です。何万本あるかな?と思いました。
ポピーはケシ科の一年草。ヨーロッパ原産です。
Wikipediaより引用しました。


ポピーはケシ科の一年草。ヨーロッパ原産です。
耐寒性の一年草で、草丈50cm~1m位になる。葉は根生葉で、羽状の切れ込みがあり無毛である。初夏に花茎を出し、上の方でよく分枝し、茎の先に直径5~10cmの赤・白・ピンクなどの4弁花を開く。現在タネとして売られているものには、八重咲きの品種が多い。ケシやオニゲシに比べるとずっと華奢で、薄い紙で作った造花のようにも見える。
Wikipediaより引用しました。


2011年06月05日
タイサンボク
大分市の佐野植物公園でみました。かなり高いところにあり撮影が難しかったです。ズームを使って撮影しました。
タイサンボクより引用しました。

・木蓮(もくれん)科。
・学名 Magnolia grandiflora
Magnolia : モクレン属
grandiflora : 大きい花の
Magnolia(マグノリア)は、
18世紀のフランス、モンペリエの植物学教授
「Magnol さん」の名前にちなむ。
・開花時期は、 6/ 1頃~ 7/10頃。
なんとなく梅雨空に似合う花です。
・北アメリカの東南部原産。
明治初期に日本へ渡来。
・大きい白いカップ形の花。
街路樹、公園樹としてときどき見かける。
背丈がかなり高くならないと花が咲かない。
・花、葉、樹形などが大きくて立派なことから
賞賛してこう名づけられた。
また、花の形を大きな盃(さかずき)に
見立てて「大盃木」、それからしだいに
「泰山木」になったとも。
・「大山木」とも書く。
・芳香あり。
タイサンボクより引用しました。

2011年06月04日
ケムリノキ
大分市の佐野植物公園でみました。多分ケムリノキで間違いないと思います。
煙の木より引用しました。

・漆(うるし)科。
・学名 Cotinus coggygria
Cotinus : ハグマノキ属
・「煙の木」っていったい何?と思ってたら、
花の時期に、糸状のけむり状のものが
ボワーッと出てきました。これが「煙」♪
・別名「白熊(はぐま)の木」
白熊 = ヤク(動物)の尾っぽの
白い毛のこと。
「霞(かすみ)の木」。霞がかってるので。
「スモークツリー」 Smoke tree
煙の木より引用しました。

2011年06月02日
ムラサキハナナ(花大根・ショカッサイ・オオアラセイトウ)
散歩中に見ました。撮影は5月下旬です。4月にも見かけたので随分長く咲く花だなあと思いました。
ハナダイコン(花大根)とはいっても野菜でありません。紫色の 4 枚の花弁が「十字架植物」であることを示しています。
空き地や土手などに一面に咲いているところがあります。20 年くらい前には,「花大根の種を差し上げます」などという投書が新聞に載るくらい,皆が欲しがっていたようですが,そのせいか現在はありふれた「雑草」になってしまったようです。しかし,群生している様は非常にきれいです。
ムラサキハナナより引用しました。

ハナダイコン(花大根)とはいっても野菜でありません。紫色の 4 枚の花弁が「十字架植物」であることを示しています。
空き地や土手などに一面に咲いているところがあります。20 年くらい前には,「花大根の種を差し上げます」などという投書が新聞に載るくらい,皆が欲しがっていたようですが,そのせいか現在はありふれた「雑草」になってしまったようです。しかし,群生している様は非常にきれいです。
ムラサキハナナより引用しました。

2011年06月01日
小手毬(こでまり)
撮影は5月初旬です。我が家の花でした。今はありません。
小手毬はバラ科。シモツケ属。原産は中国です。

小手毬はバラ科。シモツケ属。原産は中国です。
落葉低木で、高さは1.5mになる。枝は細く、先は枝垂れる。葉は互生し、葉先は鋭頭で、形はひし状狭卵形になる。春に白の小花を集団で咲かせる。この集団は小さな手毬のように見え、これが名前の由来となっている。日本では、よく庭木として植えられている。Wikipediaより引用しました。

2011年05月31日
オオデマリ
撮影は5月初旬です。緑色に変わるところを撮影したかったのですが、できませんでした。
Wikipediaより引用しました。


オオデマリ (Viburnum plicatum var. plicatum f. plicatum) はスイカズラ科の植物の一種。別名テマリバナ。。
日本原産のヤブデマリ(V. plicatum var.tomentosum)の園芸品種である。花期は5月頃で、アジサイのような白い装飾花(近年はピンクのものもある)を多数咲かせる。
原種は花序の周辺にだけ装飾花をつけるものだが、品種改良によって花序の花すべてが装飾花となったものである。このような変化は、アジサイと並行的である
Wikipediaより引用しました。


2011年05月30日
チェリーセージホットリップス
散歩中に見ました。
シソ科。サルビア属。
【別 名】ヤクヨウセージ サルビア・ミクロフィラ
【原産地】地中海沿岸 南ヨーロッパ
【花言葉】燃ゆる想い
【花 期】春~秋
【名前の由来】英名のCherry Sageから。「Salviaサルビア」の語源は、ラテン語、健康、救う、癒す」という意味の「salvare」、「死から救う」という意味の「salvara」から。
半耐寒性宿根草。 暑さや寒さに強く、挿し木や水挿しでも簡単に増やすことができます。花期が長く、甘いチェリーの香りがして、夏を過ぎると濃い赤色になります。
サルビア・ミクロフィラ・ホットリップスもチェリーセージの一種です。

シソ科。サルビア属。
【別 名】ヤクヨウセージ サルビア・ミクロフィラ
【原産地】地中海沿岸 南ヨーロッパ
【花言葉】燃ゆる想い
【花 期】春~秋
【名前の由来】英名のCherry Sageから。「Salviaサルビア」の語源は、ラテン語、健康、救う、癒す」という意味の「salvare」、「死から救う」という意味の「salvara」から。
半耐寒性宿根草。 暑さや寒さに強く、挿し木や水挿しでも簡単に増やすことができます。花期が長く、甘いチェリーの香りがして、夏を過ぎると濃い赤色になります。
サルビア・ミクロフィラ・ホットリップスもチェリーセージの一種です。

2011年05月29日
ジャーマンアイリス?
多分ジャーマンアイリスと思います。違うかも知れません。
ヤサシイエンゲイより引用しました。


ジャーマンアイリスはヨーロッパで古くから栽培されている植物でたくさんの園芸品種が存在します。もともとジャーマンアイリスという植物は自然界に存在せずドイツアヤメを元に数種類の種を掛け合わせた品種をジャーマンアイリスと呼びます。草丈は大きなものでは1mを越します。花色が非常に豊富で、白、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青、紫、黒、茶色などがあります。冬の寒さにも強く育てやすい植物で地面に近い場所に球根のような根茎を作りそれが伸びていってふえていきます。春に花茎を伸ばしてその先に3から4輪の花を咲かせます。アヤメ科。原産地はヨーロッパです。
ヤサシイエンゲイより引用しました。


2011年05月28日
アマリリス
散歩中に見ました。
アマリリスはヒガンバナ科。原産地は熱帯アメリカです。
中輪で花びらが細い目の在来種とオランダなどからポット植えで輸入される大輪で花びらの丸っこい品種があります。在来種は丈夫で比較的暑さ寒さにも強いのですが、花色が豊富で花の大きな輸入品種の方に人気があります。園芸品種の歴史も深く古くは18世紀頃から改良されています。花色はピンク、赤、白を基調として模様が入るものなど様々あります。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

アマリリスはヒガンバナ科。原産地は熱帯アメリカです。
中輪で花びらが細い目の在来種とオランダなどからポット植えで輸入される大輪で花びらの丸っこい品種があります。在来種は丈夫で比較的暑さ寒さにも強いのですが、花色が豊富で花の大きな輸入品種の方に人気があります。園芸品種の歴史も深く古くは18世紀頃から改良されています。花色はピンク、赤、白を基調として模様が入るものなど様々あります。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

2011年05月27日
オキナグサ
くじゅう花公園でみました。
白い髪を振り乱した翁の姿に似ていることが名前の由来です。赤紫色の小さな花が咲き、花が終わった後は、白い綿毛状の種子をつけ、可憐な姿が楽しめます。
幻の山野草とも言われ、絶滅の危機(絶滅危惧Ⅱ類)にある花だそうです。
今回は花が終わり白いひげをつける前の段階に出会いました。なかなかみることがないのでみたときは嬉しかったです。

白い髪を振り乱した翁の姿に似ていることが名前の由来です。赤紫色の小さな花が咲き、花が終わった後は、白い綿毛状の種子をつけ、可憐な姿が楽しめます。
幻の山野草とも言われ、絶滅の危機(絶滅危惧Ⅱ類)にある花だそうです。
今回は花が終わり白いひげをつける前の段階に出会いました。なかなかみることがないのでみたときは嬉しかったです。

2011年05月27日
ネモフィラ
くじゅう花公園でみました。
秋にタネをまくと翌年の春に花を咲かせる秋まき一年草です。花の色は空色で、春の草花にはあまりない色の花なので目立ちます。「インシグニスブルー」と呼ばれる代表的な品種です。このほかにも白、黒などの花があります。性質は丈夫で逆に過保護に育てると花つきも悪くなります。和名は「ルリカラクサ」葉っぱのカタチをよく見ると「唐草模様」に似ている?
ヤサシイエンゲイより引用しました。
「インシグニスブルー」

「スノーストーム」

「マキュラータ」

秋にタネをまくと翌年の春に花を咲かせる秋まき一年草です。花の色は空色で、春の草花にはあまりない色の花なので目立ちます。「インシグニスブルー」と呼ばれる代表的な品種です。このほかにも白、黒などの花があります。性質は丈夫で逆に過保護に育てると花つきも悪くなります。和名は「ルリカラクサ」葉っぱのカタチをよく見ると「唐草模様」に似ている?
ヤサシイエンゲイより引用しました。
「インシグニスブルー」

「スノーストーム」

「マキュラータ」

2011年05月26日
お花のパッチワーク
くじゅう花公園でみました。
その名も「春菜の畑(しゅんさいのはたけ)」。ディモールフォセカ・シレネ・ギリア・ネモフィラ・ハナビシソウ・ムルチコーレ・ナデシコ・ノースポールの8種11色の花々がパステル色の絨毯のように広がっています。
その様子はまるで絵の具を出したパレットのようです。
その①一部

その②一部

その③全体(ぼけています)

その名も「春菜の畑(しゅんさいのはたけ)」。ディモールフォセカ・シレネ・ギリア・ネモフィラ・ハナビシソウ・ムルチコーレ・ナデシコ・ノースポールの8種11色の花々がパステル色の絨毯のように広がっています。
その様子はまるで絵の具を出したパレットのようです。
その①一部

その②一部

その③全体(ぼけています)

2011年05月25日
牡丹(ボタン)
我が家の花でも紹介しましたが、ここ「くじゅう花公園」ではまだまだ開花中でした。
そろそろ咲き終わりかな?と言う状態でしたが、今までみたことがなかった色などがあって楽しめました。
どの色がお好みですか?






そろそろ咲き終わりかな?と言う状態でしたが、今までみたことがなかった色などがあって楽しめました。
どの色がお好みですか?






2011年05月21日
シラン
散歩中に見ました。白いシランをみたのは初めてです。多分シランと思いますが、間違っていたらご免なさいです。
シラン(紫蘭、学名 Bletilla striata Reichb. fil.)とはラン科シラン属の宿根草。
日本、台湾、中国が原産です。

シラン(紫蘭、学名 Bletilla striata Reichb. fil.)とはラン科シラン属の宿根草。
日本、台湾、中国が原産です。