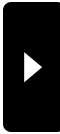2012年04月29日
白花タンポポ
近くの公園の隅で咲いていました。良く探せば結構ある花のようです。
Wikipediaより引用しました。

本種は日本在来種であり、本州関東以西、四国、九州に分布し、西の方ほど多い。 北限は定かではないが、北海道松前町龍雲院の境内で確認されている。
2月~5月にかけて白い花をつける。頭花(花に見える部分全体)のサイズは直径3.5~4.5cmほどになる。白く見える部分は舌状花(頭花を作る1つ1つの小さな花)の花冠(「花びら」に見える部分)で、中央の花柱部は黄色である。
舌状花は1つの頭花におよそ100個ほどで、他種と比べて比較的少ない。ゆえに結実する種子も比較的少ないが、他の日本在来種の主なタンポポとは違い、5倍体で単為生殖が可能である。
カンサイタンポポとケイリンシロタンポポが交雑して出来た種である事が確認されている。
他のタンポポより舌状花が少なく白色なので区別は容易である。
Wikipediaより引用しました。

2012年04月26日
シデコブシ
大分市の佐野植物公園でみました。残念ながら盛りを過ぎていてきれいな花が少なかったです。もう少し早めに行くべきでした。
Wikipediaより引用しました。

シデコブシ(幣辛夷/四手拳、学名:Magnolia stellata、シノニム:M. tomentosa )とはモクレン科の植物の一種。別名ヒメコブシ。
愛知県、岐阜県、三重県の一部に分布する落葉小高木。庭木、公園樹として見かけることがあるが、自生個体群は絶滅危惧II類に指定されている。
花期は3~4月頃で、白(ときにピンクを帯びる)の直径10cmくらいの花を咲かせる。花被片は12~18個くらい。
Wikipediaより引用しました。

2012年04月25日
2012年04月23日
シャガ
我が家の裏庭で今満開です。


人家近くの森林周辺の木陰などの、やや湿ったところに群生する。開花期は4 - 5月ごろで、白っぽい紫のアヤメに似た花をつける。花弁に濃い紫と黄色の模様がある。根茎は短く横に這い、群落を形成する。草丈は高さは50 - 60 センチ・メートル程度までになり、葉はつやのある緑色、左右から扁平になっている。いわゆる単面葉であるが、この種の場合、株の根本から左右どちらかに傾いて伸びて、葉の片面だけを上に向け、その面が表面のような様子になり、二次的に裏表が生じている。Wikipediaより引用しました。
学名の種小名はjaponica(「日本の」という意味)ではあるが、シャガは中国原産で、かなり古くに日本に入ってきた帰化植物である。三倍体のため種子が発生しない。このことから日本に存在する全てのシャガは同一の遺伝子を持ち、またその分布の広がりは人為的に行われたと考えることができる。したがって、人為的影響の少ない自然林内にはあまり自生しない。スギ植林の林下に見られる場所などは、かつては人間が住んでいた場所である可能性が高い。そういう場所には、チャノキなども見られることが多い。中国には二倍体の個体があり花色、花径などに多様な変異があるという。東京都でレッドリストの準絶滅危惧種に指定されている。


2012年04月22日
寒アヤメ
私が良く行くパン屋さんの花壇にありました。撮影は4月上旬です。
syuさんのHPより引用しました。

地中海の東部沿岸に分布しています。乾燥した岩礫地の斜面に生え、高さは20~30センチになります。葉は非常に細く、幅は3ミリほどです。晩秋から冬の終わりにかけて花を咲かせます。花はふつうスミレ色ですが、まれにピンク色や白色もあります。花披片の真ん中には、オレンジ色の筋があります。
syuさんのHPより引用しました。

2012年04月21日
ジンチョウゲ
我が家にも古株のジンチョウゲがあったのですが、突然枯れてしまいました。
ので、新しく買ってきて母と一緒に植えました。路地植えをしました。どれくらいで花が咲くか分かりませんが、早く咲いて欲しいです。
漢字では「沈丁花」と書き、花の香りが沈香、花姿が丁字に似ているところに由来するとされます。特徴はなんと言っても、上品な甘い香りを放つ花です。庭木のほか、鉢植えにもされます。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

このような木になって欲しいです。

ので、新しく買ってきて母と一緒に植えました。路地植えをしました。どれくらいで花が咲くか分かりませんが、早く咲いて欲しいです。
漢字では「沈丁花」と書き、花の香りが沈香、花姿が丁字に似ているところに由来するとされます。特徴はなんと言っても、上品な甘い香りを放つ花です。庭木のほか、鉢植えにもされます。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

このような木になって欲しいです。

2012年04月19日
ムラサキハナナ
私が通院している病院の薬局の花壇にありました。4月上旬の撮影です。
学名:Orychophragmus violaceus
別名:ショカツサイ(諸葛采),オオアラセイトウ,ハナダイコン(花大根)
花期:春

学名:Orychophragmus violaceus
別名:ショカツサイ(諸葛采),オオアラセイトウ,ハナダイコン(花大根)
花期:春
ハナダイコン(花大根)とはいっても野菜でありません。紫色の 4 枚の花弁が「十字架植物」であることを示しています。ムラサキハナナより引用しました。
空き地や土手などに一面に咲いているところがあります。20 年くらい前には,「花大根の種を差し上げます」などという投書が新聞に載るくらい,皆が欲しがっていたようですが,そのせいか現在はありふれた「雑草」になってしまったようです。しかし,群生している様は非常にきれいです。
別名のショカツサイ(諸葛采)は中国の呼び名,オオアラセイトウの「アラセイトウ」とはストックのことです。

2012年04月17日
はなもも
私が通院している病院の花壇で見ました。まだ蕾状態もあってこれから開花するようです。
ひなまつりの花として日本でも古くから馴染みの深い落葉性の木です。花色はピンクの他に白、赤などがあり、花の形もキクのようなかたちの花を咲かせるものなどがあります。原産は中国ですが品種改良が行われたのはほとんど日本です。ハナモモはその名の通り花を鑑賞する事を目的とされており、実は小さくて食用に適しません。
ヤサシイエンゲイより引用しました。



ひなまつりの花として日本でも古くから馴染みの深い落葉性の木です。花色はピンクの他に白、赤などがあり、花の形もキクのようなかたちの花を咲かせるものなどがあります。原産は中国ですが品種改良が行われたのはほとんど日本です。ハナモモはその名の通り花を鑑賞する事を目的とされており、実は小さくて食用に適しません。
ヤサシイエンゲイより引用しました。



2012年04月15日
シモクレン

我が家の前のお宅に咲いていました。昨日は「ハクモクレン」を載せましたが、やはり、モクレンと言えば、この色でしょうか?
モクレン(木蓮) は、別名を マグノリア(Magnolia) と呼ばれる モクレン科モクレン属の落葉小高木です。通常、モクレン(木蓮)と言えば、濃紅色の花を咲かせる シモクレン(紫木蓮) のことを言います。白花を咲かせるのは、 ハクモクレン(白木蓮) です。 春、新葉が出る前に、骨格がしっかりした木の枝先に、濃紅色で卵形の大きな花を咲かせます。 花は上向きに咲き、全開せず半開状(開ききらない状態)に咲きます。 花色が濃い紅色は花弁の外側でけで、花弁の内側は白または白味がかった極薄紅色です。
シモクレンより引用しました。
2012年04月14日
ハクモクレン
大分県の別府にある「志高湖」でみました。志高湖は山の中にあります。その関係か分かりませんが、まだ咲いていました。でも、やはり近くに行くと花びらが散っていました。きれいでしたが、散る前のハクモクレンを見ることができなくてちょっぴり残念でした。
・木蓮(もくれん)科。
・学名 Magnolia denudata または
Magnolia heptapeta
Magnolia : モクレン属
denudata : 裸の、露出した
Magnolia(マグノリア)は、
18世紀のフランス、モンペリエの植物学教授
「Magnol さん」の名前にちなむ。
・開花時期は、 3/10頃~ 4/10頃。
・白い清楚な花。
花びらの幅が広く、厚みがある。
花は上向きに閉じたような形で咲く。
全開しない。これが辛夷と違うところ。
・開花しているときの風景は、
白い小鳥がいっぱい木に止まっているように
見える。
・花びらは太陽の光を受けて
南側がふくらむため、花先は北側を指す。
(そういえば「つぼみ」の頃は
片方にそり返っている)
このことから、「磁石の木」と
呼ばれることもある。
白木蓮より引用しました。

・木蓮(もくれん)科。
・学名 Magnolia denudata または
Magnolia heptapeta
Magnolia : モクレン属
denudata : 裸の、露出した
Magnolia(マグノリア)は、
18世紀のフランス、モンペリエの植物学教授
「Magnol さん」の名前にちなむ。
・開花時期は、 3/10頃~ 4/10頃。
・白い清楚な花。
花びらの幅が広く、厚みがある。
花は上向きに閉じたような形で咲く。
全開しない。これが辛夷と違うところ。
・開花しているときの風景は、
白い小鳥がいっぱい木に止まっているように
見える。
・花びらは太陽の光を受けて
南側がふくらむため、花先は北側を指す。
(そういえば「つぼみ」の頃は
片方にそり返っている)
このことから、「磁石の木」と
呼ばれることもある。
白木蓮より引用しました。

2012年04月12日
牡丹
我が家の牡丹が1個開花しました。今年は蕾も多くて、母も喜んでいました。2階から母が開花しているのを見つけました。昨日が暖かかったので開花も一気に進んだようです。全部開花するまで毎日が楽しみです。
Wikipediaより引用しました。


ボタン(牡丹、学名:Paeonia suffruticosa)は、ボタン科ボタン属の落葉小低木。
または、ボタン属(Paeonia)の総称。 別名は「富貴草」「富貴花」「百花王」「花王」「花神」「花中の王」「百花の王」「天香国色」 「名取草」「深見草」「二十日草(廿日草)」「忘れ草」「鎧草」「ぼうたん」「ぼうたんぐさ」など多数。
以前はキンポウゲ科に分類されていたが、おしべ・花床の形状の違いから現在はシャクヤクとともにビワモドキ目に編入され、独立のボタン科とされている。
Wikipediaより引用しました。


2012年04月08日
トサミズキ
我が家の花です。あまり目立たない花ですが、好きな花の一つです。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

四国に分布する落葉性の低木~小高木です。高知(土佐)の蛇紋岩地に野生のものが多く見られるため、この名前があります。ミズキと名前が付きますが、ミズキ科ではなく、マンサク科の植物です。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

2012年04月05日
桜
近所の花です。大分の桜(ソメイヨシノ)は今が見頃のようです。撮影時にはひらひら花びらが舞っていました。
Wikipediaより引用しました。
サクラは、バラ科サクラ属サクラ亜属に分類される木であり、落葉広葉樹である。春に白色や淡紅色から濃紅色の花を咲かせ、日本人に古くから親しまれている。また、果実を食用とするほか、花や葉の塩漬けも食品などに利用され、海外においては、一般的に果樹としての役割のほうが重視された。環境がよければ寿命は非常に長く、老木として著名な日本五大桜の内神代桜は樹齢が1800年を超えているとされる。
Wikipediaより引用しました。

2012年03月27日
豊後
豊後は梅の系統のひとつで、ウメとアンズの
中間品種です。枝が太く葉が大きいのが特徴。
いっこん染めのようなごくうすいピンクですが
ガクが赤いので遠目にはほどよいピンク色に
見えます。秋になるとこずえや葉が紫紅色に
なります。

中間品種です。枝が太く葉が大きいのが特徴。
いっこん染めのようなごくうすいピンクですが
ガクが赤いので遠目にはほどよいピンク色に
見えます。秋になるとこずえや葉が紫紅色に
なります。

2012年03月11日
クリスマスローズ
我が家の庭にもようやくクリスマスローズが開花しました。今年は沢山咲いて母も喜んでいました。下向きに咲く花ですのでなかなか開花しても全体を見ることは難しい花ですが、幸い何個か上向きにさいていましたので撮影ができました。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

クリスマスローズを含む、キンポウゲ科ヘレボラス属はヨーロッパから西アジアにかけておよそ20種、中国に1種が知られる、毎年花を咲かせる多年草です。「クリスマスローズ」の名前は本来ヘレボラス属の中でも「ニゲル」という一つの種につけられた名前ですが、日本ではヘレボラス属全体を指すのが一般的です。言い換えれば、前者は「狭い意味でのクリスマスローズ」、後者は「広い意味でのクリスマスローズ」ともいえるでしょう。
日本では春に開花するオリエンタリスを元とした園芸品種が広く普及しており、それを見てなぜクリスマスと名前が付くのか首をかしげる方も時々おられますが、狭い意味でのクリスマスローズ「ニゲル」が12月末頃に開花すると言うと、納得していただけると思います。ちなみに、イギリスではオリエンタリスのことはレンテンローズと呼びます。これはレント(四旬節)の頃に咲くので名付けられました。
クリスマスローズ(ニゲル)が日本に入ってきたのは明治初期と言われています。観賞用ではなく、薬草として試験的に植えられたのが栽培の最初とされます。
属名のヘレボラスはギリシア語のヘレイン(殺す)とボーラ(食べ物)の2語からなります。これは茎葉、根などにに有毒成分のサポニンを有するところにちなみ、「食べたら死ぬ」ということでしょう。
ヤサシイエンゲイより引用しました。

2012年02月19日
ペーパーホワイト
フサザキスイセンで、分類的には原種タゼッタの仲間。原産地は地中海沿岸地方で、シルクロードを経由して中国にもたらされ、日本へは平安時代に遣唐使などによって薬草として持ち込まれました。それが野生化してニホンズイセンとなったといいます。本種も同じ経路を辿ったものと考えられています。ニホンスイセンの特徴は中央の黄色いことですが、このペーパーホワイトは副花冠が白色をしています。ニホンズイセンに先駆けて咲く、寒咲きのスイセンです。一見、園芸品種のようですが、原種水仙の一種です。ペーパーホワイト、グランドソレドール、ニホンスイセンの順に咲いていくことが多いようです。この花によく似た『ガリル』という品種があり、こちらも地中海原産の原種のようですが、違いについての詳しい文献が見当たりません。ニホンスイセンとほぼ同じ時期に咲き、個人的意見ではこちらの方が花つきがいいように思えます。
ペーパーホワイトより引用しました。

2012年02月18日
冬の花
ぶらぶら散歩をしていると、どこからともなく甘い良い香りがしてきます。きょろきょろ周りを見渡すと、黄色の花がありました。
この花はどうやら「ソシンロウバイ」のようです。
ギリシャ語で「冬+花」で「冬の花」をあらわすものだそうです。原産地は中国で、日本には17世紀頃渡来したようです。
本当に蝋細工の花のようです。てかてか光っています。また、この花が咲くのをみることができて、1年経ったんだなあと思います。
明日も散歩していて見つけた花を紹介します。

この花はどうやら「ソシンロウバイ」のようです。
ギリシャ語で「冬+花」で「冬の花」をあらわすものだそうです。原産地は中国で、日本には17世紀頃渡来したようです。
本当に蝋細工の花のようです。てかてか光っています。また、この花が咲くのをみることができて、1年経ったんだなあと思います。
明日も散歩していて見つけた花を紹介します。

2012年02月11日
マーガレット モリンバ
この花も撮影は12月中旬でした。
マーガレット、語源はギリシア語で、”真珠”を意味するマーガレッテからきています。原産はアフリカ西方マデイラ島やカナリヤ群島です。
大陸の西方で発見されたマーガレットは、200年以上の年月をかけて改良され、ついにはシンジェンタによって開発された”モリンバ”大陸の東の果ての国でも楽しむことができるようになりました。

マーガレット、語源はギリシア語で、”真珠”を意味するマーガレッテからきています。原産はアフリカ西方マデイラ島やカナリヤ群島です。
大陸の西方で発見されたマーガレットは、200年以上の年月をかけて改良され、ついにはシンジェンタによって開発された”モリンバ”大陸の東の果ての国でも楽しむことができるようになりました。

2012年02月09日
久々の更新です
考えるところがあって暫くブログから離れていました。ただ、心の何処かにはブログのことが気になっていました。やっと踏ん切りがついたのでまた再開することにしました。
と、言っても花の素材がありません。ちょこちょこ撮影はしていたのですが、12月31日が最後の花の撮影日です。季節とは合わない花が多く登場すると思いますが、そこは勘弁して下さい。
それでは、花の紹介です。「シクラメン」です。
サクラソウ科シクラメン属。原産地は地中海沿岸です。
我が家の花です。これが12月31日に撮影した最後の花です。普通のシクラメンと違ってかなり大きいなあと思います。正札1300円の所を300円で母が買って来ました。かなりのお得な花だと思います。

と、言っても花の素材がありません。ちょこちょこ撮影はしていたのですが、12月31日が最後の花の撮影日です。季節とは合わない花が多く登場すると思いますが、そこは勘弁して下さい。
それでは、花の紹介です。「シクラメン」です。
サクラソウ科シクラメン属。原産地は地中海沿岸です。
我が家の花です。これが12月31日に撮影した最後の花です。普通のシクラメンと違ってかなり大きいなあと思います。正札1300円の所を300円で母が買って来ました。かなりのお得な花だと思います。