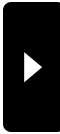2009年07月31日
サポナリア+万両の花
今日は地味で目立たない花です。サポナリアは近所、万両は我が家の花です。
「サポナリア」はナデシコ科。サポナリア(シャボンソウ)属。原産地はヨーロッパ、西アジアです。
別名シャボンソウ、ソープワート。草丈40~80センチになります。直立する茎はよく分岐し、夏から秋にかけ茎の先端にたくさんの小さな花を咲かせます。花色は白とピンクがあります。花には一重咲きのものと、八重咲きのものがあります。写真のサポナリアは、八重咲き種と思います。

「万両の花」はセンリョウ(ヤブコウジ)科。ヤブコウジ(アルディシア)属。原産地は日本からインド北部です。
万両の花は7~8月頃に下向きに咲き、 12月頃から冬にかけて実が赤くなります。万両のなかには実が白い種類もあります。
万両の実はずーっと長い間残ります(冬にできた実が次の冬まで残っていることもあるそうです)。
実は正月の縁起物に使われます。
撮影しずらい花です。

「サポナリア」はナデシコ科。サポナリア(シャボンソウ)属。原産地はヨーロッパ、西アジアです。
別名シャボンソウ、ソープワート。草丈40~80センチになります。直立する茎はよく分岐し、夏から秋にかけ茎の先端にたくさんの小さな花を咲かせます。花色は白とピンクがあります。花には一重咲きのものと、八重咲きのものがあります。写真のサポナリアは、八重咲き種と思います。

「万両の花」はセンリョウ(ヤブコウジ)科。ヤブコウジ(アルディシア)属。原産地は日本からインド北部です。
万両の花は7~8月頃に下向きに咲き、 12月頃から冬にかけて実が赤くなります。万両のなかには実が白い種類もあります。
万両の実はずーっと長い間残ります(冬にできた実が次の冬まで残っていることもあるそうです)。
実は正月の縁起物に使われます。
撮影しずらい花です。

2009年07月30日
ノウゼンカズラ
我が家の花です。今年は枝が折れたり、剪定したのでもう咲かないかな?と思っていました。先日花が数輪咲いているのを発見しました。早速ぱちりです。
「ノウゼンカズラ」はノウゼンカズラ科。ノウゼンカズラ属。ノウゼンカズラは中国原産の落葉ツル植物です。幹から気根を出して樹木等に登る、這い登り型のツル植物です。6月の中頃から8月まで赤朱色の花を次々と咲かせます。落ち着きのある花であり、なんだかオリエンタルなイメージがあります。
今年もみることができて良かったです。花がぼとぼと落ちて掃除に困る花ですけど、咲いてる間はきれいです。



「ノウゼンカズラ」はノウゼンカズラ科。ノウゼンカズラ属。ノウゼンカズラは中国原産の落葉ツル植物です。幹から気根を出して樹木等に登る、這い登り型のツル植物です。6月の中頃から8月まで赤朱色の花を次々と咲かせます。落ち着きのある花であり、なんだかオリエンタルなイメージがあります。
今年もみることができて良かったです。花がぼとぼと落ちて掃除に困る花ですけど、咲いてる間はきれいです。



2009年07月29日
コデチア
花の名前が分からず苦労しました。最初聞いたときは「コデッチャ」でした。その名前では検索でヒットせず、「コデチャ」にしてみました。何件かヒットしました。でも、正体不明です。
最後に「コデチア」にしてみました。かなりヒットしました。しかし、それでも謎の花です。
どれが本当の名前でしょうか?
アカバナ科の仲間のようです。かよわい花の印象を受けました。病院の職員の方が育てていました。沢山開花すると良いなあと思いました。
花言葉:「変わらぬ熱愛」とか出てました。
どなたかこの花に関する情報を教えて下さい。職員の方も知りたがっていましたので宜しくお願いします。


最後に「コデチア」にしてみました。かなりヒットしました。しかし、それでも謎の花です。
どれが本当の名前でしょうか?
アカバナ科の仲間のようです。かよわい花の印象を受けました。病院の職員の方が育てていました。沢山開花すると良いなあと思いました。
花言葉:「変わらぬ熱愛」とか出てました。
どなたかこの花に関する情報を教えて下さい。職員の方も知りたがっていましたので宜しくお願いします。


2009年07月28日
エンジェルトランペット+チョウセンアサガオ
我が家の花と近所でみた花です。エンジェルトランペットは我が家の花です。チョウセンアサガオは近所の花です。
「エンジェルトランペット」はナス科。キダチチョウセンアサガオ(ブルグマンシア)属。原産地は中南米です。
ダツラとも呼ばれ、花はアサガオに似ています。花の直径は10センチ程度ですが長さは20センチ程度にまで成長します。全体的には下に向いて垂れるように咲くのが特長です。 色は白~黄色、ややオレンジ系の3種があります。


「チョウセンアサガオ」はナス科。チョウセンアサガオ属。原産地は東南アジアです。江戸時代から明治時代に日本に入ってきた帰化植物です。
高さ約1メートルの一年草で、夏から初秋にかけて白く長いロート状の花を咲かせます。
中国名では「曼陀羅華(マンダラゲ)」と呼ばれ、江戸時代の蘭学医・華岡清洲が1804年にこの植物から得た麻酔薬で外科手術をしたことで有名です。

「エンジェルトランペット」はナス科。キダチチョウセンアサガオ(ブルグマンシア)属。原産地は中南米です。
ダツラとも呼ばれ、花はアサガオに似ています。花の直径は10センチ程度ですが長さは20センチ程度にまで成長します。全体的には下に向いて垂れるように咲くのが特長です。 色は白~黄色、ややオレンジ系の3種があります。


「チョウセンアサガオ」はナス科。チョウセンアサガオ属。原産地は東南アジアです。江戸時代から明治時代に日本に入ってきた帰化植物です。
高さ約1メートルの一年草で、夏から初秋にかけて白く長いロート状の花を咲かせます。
中国名では「曼陀羅華(マンダラゲ)」と呼ばれ、江戸時代の蘭学医・華岡清洲が1804年にこの植物から得た麻酔薬で外科手術をしたことで有名です。

2009年07月27日
タイマツバナ+ボッグセージ+不明
近所で見かけた花です。撮影は6月中旬です。名前が分からずそのままになってました。
偶然名前を知ったので載せます。多分間違いないと思います。
「タイマツバナ」はシソ科。ヤグルマハッカ属。松明のような真っ赤な炎を連想させる花です。種類としてはモナルダの仲間だそうですが,サルビアにイメージが似ていると思います。
花が終わった状態です。残念です。

次は「ボッグセージ」です。シソ科。アキギリ属。原産地はブラジル~ウルグアイ~アルゼンチンです。涼しげなスカイブルー花の下唇(lower lip)の中にある白い線は,受粉のための虫を導く蜜標(honey guide)と言われるもので,特に比較的浅い花筒(corolla tube)を持つ青い花のサルビアに多く見られるものです.花蜂はこれを目印に花粉や蜜を探しに来ます。
写りが悪いですね。すいません。

最後は不明です。同じくシソ科の仲間かな?と思います。

名前が分かりました。
*シソ科、ホットリップス、チェリーセージの仲間です。
偶然名前を知ったので載せます。多分間違いないと思います。
「タイマツバナ」はシソ科。ヤグルマハッカ属。松明のような真っ赤な炎を連想させる花です。種類としてはモナルダの仲間だそうですが,サルビアにイメージが似ていると思います。
花が終わった状態です。残念です。

次は「ボッグセージ」です。シソ科。アキギリ属。原産地はブラジル~ウルグアイ~アルゼンチンです。涼しげなスカイブルー花の下唇(lower lip)の中にある白い線は,受粉のための虫を導く蜜標(honey guide)と言われるもので,特に比較的浅い花筒(corolla tube)を持つ青い花のサルビアに多く見られるものです.花蜂はこれを目印に花粉や蜜を探しに来ます。
写りが悪いですね。すいません。

最後は不明です。同じくシソ科の仲間かな?と思います。

名前が分かりました。
*シソ科、ホットリップス、チェリーセージの仲間です。
2009年07月26日
カラー
我が家の花です。母が買ってきました。妹と出かけて買ってきました。こうして出かけることができるようになったぐらい回復して嬉しいです。
さて、「カラー」ですが、サトイモ科。ザンデスキア属。原産地は南アフリカです。仏炎苞や葉が美しいものがあり観葉植物として栽培されます。
こうしたものは、カラー(Calla)またはカラーリリー(calla lily)と呼ばれます。
別名:オランダカイウ
体調が悪いので記事も短めになります。すいません。ここまで書くのに30分かかりました。


さて、「カラー」ですが、サトイモ科。ザンデスキア属。原産地は南アフリカです。仏炎苞や葉が美しいものがあり観葉植物として栽培されます。
こうしたものは、カラー(Calla)またはカラーリリー(calla lily)と呼ばれます。
別名:オランダカイウ
体調が悪いので記事も短めになります。すいません。ここまで書くのに30分かかりました。


2009年07月25日
ピンぼけですが・・・
私が通院している病院でみた花です。ピンぼけですが・・・強引に載せます。
まずは「セイヨウニンジンボク」です。クマツヅラ科。ハマゴウ属。原産地は地中海沿岸~西アジアです。薄紫色の花が涼しげなのと、葉の形と色が特徴です。盛夏期、花が少なくなる時期に涼しげな花を咲かせる花木です。花穂が次々と咲くため開花期が長いです。まだみたことはないですが白花もあるようです。


次は「コムラサキの花」です。クマツヅラ科。ムラサキシキブ属。原産地は日本、中国、台湾です。7~8月頃に、葉腋の少し上から集散花序を出し、淡紫色の小さな花を密につけます。

最後は「ギボウシ」です。紫色をみました。ユリ科。ギボウシ属。原産地は日本、中国です。強い日光と猛暑が苦手のようで日焼けしてしまうらしいです。イギリスや北欧では夏は日本より涼しいので、ガーデニングとしてよく使われるそうです。

まずは「セイヨウニンジンボク」です。クマツヅラ科。ハマゴウ属。原産地は地中海沿岸~西アジアです。薄紫色の花が涼しげなのと、葉の形と色が特徴です。盛夏期、花が少なくなる時期に涼しげな花を咲かせる花木です。花穂が次々と咲くため開花期が長いです。まだみたことはないですが白花もあるようです。


次は「コムラサキの花」です。クマツヅラ科。ムラサキシキブ属。原産地は日本、中国、台湾です。7~8月頃に、葉腋の少し上から集散花序を出し、淡紫色の小さな花を密につけます。

最後は「ギボウシ」です。紫色をみました。ユリ科。ギボウシ属。原産地は日本、中国です。強い日光と猛暑が苦手のようで日焼けしてしまうらしいです。イギリスや北欧では夏は日本より涼しいので、ガーデニングとしてよく使われるそうです。

Posted by ひろぼう at
05:10
│Comments(0)
2009年07月24日
デュランタタカラヅカ+メディニラマグニフィカ
大分市の佐野植物公園の温室でみました。タカラヅカはみたいと思っていた花でみることができて良かったです。メディニラマグニフィカは花が咲いているのは初めてみました。
「デュランタタカラヅカ」はクマツヅラ科。ハリマツリ(デュランタ)属。原産地は熱帯アメリカ。品種名タカラヅカは、デュランタ・レペンスの改良種です。色が鮮やかで多花性なので、最近、人気の出て来た品種です。

「メディニラマグニフィカ」はノボタン科。メディニラ属。原産地はフィリピンです。淡紅色の花が30センチほど房になって垂れ下がり、初夏から長期間咲き続けます。
淡紅色の部分は苞で、その先に丸い蕾が野ブドウのように沢山つきます。

「デュランタタカラヅカ」はクマツヅラ科。ハリマツリ(デュランタ)属。原産地は熱帯アメリカ。品種名タカラヅカは、デュランタ・レペンスの改良種です。色が鮮やかで多花性なので、最近、人気の出て来た品種です。

「メディニラマグニフィカ」はノボタン科。メディニラ属。原産地はフィリピンです。淡紅色の花が30センチほど房になって垂れ下がり、初夏から長期間咲き続けます。
淡紅色の部分は苞で、その先に丸い蕾が野ブドウのように沢山つきます。

2009年07月23日
ヤマボウシ他
少し前の花です。パソコンで眠っていました。
まずは「ヤマボウシ」です。ミズキ科。ミズキ属。高さ5~10メートルです。幹は灰褐色です。葉は対生し、楕円(だえん)形または卵円形で長さ4~12センチ、全縁でやや波打ちます。花は6~7月に開き、淡黄色で小さく、多数が球状に集合し、その外側に大形白色の総ほう片が4枚あり、花弁のように見えます。


次は「白いランタナ」です。クマツヅラ科。ランタナ属。非耐寒性常緑低木です。
色が変わらない分面白みはないのかも知れません。

次は「ヒルザキツキミソウ」です。アカバナ科。マツヨイグサ属。ヒルザキツキミソウは北米南部原産の多年草です。観賞用として栽培されていますが、近年法面の緑化においてワイルドフラワーとしても使われています。花色は白から薄いピンク色。マツヨイグサの仲間は夕方から花開き、夜間に蛾などによって花粉を媒介していますが、ヒルザキツキミソウは名前のごとく、昼間にも開花しています。

まずは「ヤマボウシ」です。ミズキ科。ミズキ属。高さ5~10メートルです。幹は灰褐色です。葉は対生し、楕円(だえん)形または卵円形で長さ4~12センチ、全縁でやや波打ちます。花は6~7月に開き、淡黄色で小さく、多数が球状に集合し、その外側に大形白色の総ほう片が4枚あり、花弁のように見えます。


次は「白いランタナ」です。クマツヅラ科。ランタナ属。非耐寒性常緑低木です。
色が変わらない分面白みはないのかも知れません。

次は「ヒルザキツキミソウ」です。アカバナ科。マツヨイグサ属。ヒルザキツキミソウは北米南部原産の多年草です。観賞用として栽培されていますが、近年法面の緑化においてワイルドフラワーとしても使われています。花色は白から薄いピンク色。マツヨイグサの仲間は夕方から花開き、夜間に蛾などによって花粉を媒介していますが、ヒルザキツキミソウは名前のごとく、昼間にも開花しています。

2009年07月22日
ストケシア
我が家の花です。
「ストケシア」はキク科。ストケシア属。ストケシアは北アメリカの南西部(南カリフォルニア、フロリダ、ルイジアナなど)に一種が分布する多年生の植物です。
日本に渡来してきたのは大正の初めで、昭和の初期に人気が出て広く普及したと言われています。花はヤグルマギクを大きくしたような感じで、青、紫、白、黄色、ピンクなど花色は豊富で、園芸品種も存在します。別名のルリギクはブルー系の花色から来ているのでしょう。主に初夏を彩る花ですが、原産地の一部暖地では冬でも休まず花を咲かせ続けるそうです。
生育旺盛で繁殖力も強く、切れた根からも芽を出して育っていきます。花茎の先端が枝分かれしてたくさんの花を咲かせるので1株だけでも非常にボリュームがあります。
ストケシアという名前はイギリスの植物学者ストークスにちなんで名付けられました。
(ヤサシイエンゲイより引用しました)


「ストケシア」はキク科。ストケシア属。ストケシアは北アメリカの南西部(南カリフォルニア、フロリダ、ルイジアナなど)に一種が分布する多年生の植物です。
日本に渡来してきたのは大正の初めで、昭和の初期に人気が出て広く普及したと言われています。花はヤグルマギクを大きくしたような感じで、青、紫、白、黄色、ピンクなど花色は豊富で、園芸品種も存在します。別名のルリギクはブルー系の花色から来ているのでしょう。主に初夏を彩る花ですが、原産地の一部暖地では冬でも休まず花を咲かせ続けるそうです。
生育旺盛で繁殖力も強く、切れた根からも芽を出して育っていきます。花茎の先端が枝分かれしてたくさんの花を咲かせるので1株だけでも非常にボリュームがあります。
ストケシアという名前はイギリスの植物学者ストークスにちなんで名付けられました。
(ヤサシイエンゲイより引用しました)


2009年07月21日
花石榴(はなざくろ)
私が良く行く「おばあちゃんの散歩道」(私が勝手に命名)にありました。
今まで石榴(ざくろ)の花は一重しかみたことがなかったので何の花だろうと思いました。
八重の石榴(ざくろ)と分かりました。八重の石榴は実がつかず「花石榴(はなざくろ)」と呼ばれていることも分かりました。
「花石榴(はなざくろ)」はザクロ科。ザクロ属。小アジア原産の落葉小高木。日本には古い時代に渡来したとのことです。高さは5~6mになり、よく分枝し、老木になると幹が捩(よじ)れるようです。
若枝は4稜があり、短枝の先は刺となるそうです。葉は対生し、長さ2~5センチの長楕円形で全縁です。
6~7月、直径約5㎝の朱赤色の花を開きます。花弁は5枚で、薄くて皺があります。萼は6浅裂します。



今まで石榴(ざくろ)の花は一重しかみたことがなかったので何の花だろうと思いました。
八重の石榴(ざくろ)と分かりました。八重の石榴は実がつかず「花石榴(はなざくろ)」と呼ばれていることも分かりました。
「花石榴(はなざくろ)」はザクロ科。ザクロ属。小アジア原産の落葉小高木。日本には古い時代に渡来したとのことです。高さは5~6mになり、よく分枝し、老木になると幹が捩(よじ)れるようです。
若枝は4稜があり、短枝の先は刺となるそうです。葉は対生し、長さ2~5センチの長楕円形で全縁です。
6~7月、直径約5㎝の朱赤色の花を開きます。花弁は5枚で、薄くて皺があります。萼は6浅裂します。



2009年07月20日
散歩中にみかけた花たち
散歩中にみかけた花たちです。野に咲く花です。結構きれいな花があって驚きます。
まずは「シロツメクサ」です。マメ科。シャジクソウ属。シロツメクサはヨーロッパ原産の帰化植物です。クローバーとも呼ばれます。日本に渡来したのは江戸時代であり、花を乾燥してガラス器などの緩衝剤として詰め物にしたものから発芽したものであるといいます。地表直下から地表を匍匐する地下茎があり、所々から葉や花を付ける。3つの小葉を付けるのが普通であるが、4~6枚の小葉をつけることもあり「幸せを呼ぶ四つ葉のクローバー」として親しまれています。

次は「アカツメクサ」です。マメ科。シャジクソウ属。
アカツメクサ(赤詰草) は、野原や畑で見かける「シロツメクサ」 によく似た姿形をしており、花色は赤紫をした多年草です。小花がたくさん集って(集合花で)可愛らしい球状の花を形作っています。アカツメクサ(赤詰草)の葉や茎には、薄い毛が生えています。葉の中央には白いV字型をした斑紋があり、葉は大抵3枚から成りますが、まれに4枚のものもあります。アカツメクサ(赤詰草)は、当初は鶏や兎等の牧草として南欧から輸入されたものですが、その後は野生化しています。

次は「ワルナスビ」です。ナス科。ナス属。ワルナスビは名前の通り、嫌われ者の帰化植物です。茎に鋭い棘があり、手鎌で刈り取るには革製の手袋などの防御が必要です。花や葉の形からはナスの仲間であることが容易にわかります。花は可憐であるが、人間にとって鋭い棘は悪者であり、害草とされます。
ワルナスビは北アメリカ原産であり、牧草の種子に混ざって輸入されてしまったそうです。当初は牧草地でよく見かけたものであったが、最近は道端や耕作地の周辺でも時折見かけるようになりました。地下茎で繁殖するので、いったん侵入するとなかなか根絶できないようです。生長にはある程度の栄養分を必要とするらしく、荒れ地にはあまり見かけない花です。

最後は「ヤブガラシ」です。ブドウ科。ヤブガラシ属。ヤブガラシは、地下に縦横に伸びた根茎で芽を出して繁殖して、茎は、生長が早く細い巻きひげは、四方八方に伸びて他の植物にからみついて、覆いかぶさります。
繁殖力は非常に旺盛で、たちまち全体を覆い、藪を枯らしてしまうということから、藪(やぶ)枯らしといわれ、ヤブガラシの名が付きました。
ほおっておくと、家の周りに生えた、ヤブガラシが全体を覆い、いかに、もみすぼらしく見えることから貧乏カズラの別名もあります。
また、地方名では、ヤブガラミ、ヤブタオシ、ジャングルなどという名もあります。

まずは「シロツメクサ」です。マメ科。シャジクソウ属。シロツメクサはヨーロッパ原産の帰化植物です。クローバーとも呼ばれます。日本に渡来したのは江戸時代であり、花を乾燥してガラス器などの緩衝剤として詰め物にしたものから発芽したものであるといいます。地表直下から地表を匍匐する地下茎があり、所々から葉や花を付ける。3つの小葉を付けるのが普通であるが、4~6枚の小葉をつけることもあり「幸せを呼ぶ四つ葉のクローバー」として親しまれています。

次は「アカツメクサ」です。マメ科。シャジクソウ属。
アカツメクサ(赤詰草) は、野原や畑で見かける「シロツメクサ」 によく似た姿形をしており、花色は赤紫をした多年草です。小花がたくさん集って(集合花で)可愛らしい球状の花を形作っています。アカツメクサ(赤詰草)の葉や茎には、薄い毛が生えています。葉の中央には白いV字型をした斑紋があり、葉は大抵3枚から成りますが、まれに4枚のものもあります。アカツメクサ(赤詰草)は、当初は鶏や兎等の牧草として南欧から輸入されたものですが、その後は野生化しています。

次は「ワルナスビ」です。ナス科。ナス属。ワルナスビは名前の通り、嫌われ者の帰化植物です。茎に鋭い棘があり、手鎌で刈り取るには革製の手袋などの防御が必要です。花や葉の形からはナスの仲間であることが容易にわかります。花は可憐であるが、人間にとって鋭い棘は悪者であり、害草とされます。
ワルナスビは北アメリカ原産であり、牧草の種子に混ざって輸入されてしまったそうです。当初は牧草地でよく見かけたものであったが、最近は道端や耕作地の周辺でも時折見かけるようになりました。地下茎で繁殖するので、いったん侵入するとなかなか根絶できないようです。生長にはある程度の栄養分を必要とするらしく、荒れ地にはあまり見かけない花です。

最後は「ヤブガラシ」です。ブドウ科。ヤブガラシ属。ヤブガラシは、地下に縦横に伸びた根茎で芽を出して繁殖して、茎は、生長が早く細い巻きひげは、四方八方に伸びて他の植物にからみついて、覆いかぶさります。
繁殖力は非常に旺盛で、たちまち全体を覆い、藪を枯らしてしまうということから、藪(やぶ)枯らしといわれ、ヤブガラシの名が付きました。
ほおっておくと、家の周りに生えた、ヤブガラシが全体を覆い、いかに、もみすぼらしく見えることから貧乏カズラの別名もあります。
また、地方名では、ヤブガラミ、ヤブタオシ、ジャングルなどという名もあります。

2009年07月19日
サフランモドキ
散歩中にみました。花色が薄いのですが多分サフランモドキと思います。
「サフランモドキ」はヒガンバナ科。ゼフィランサス属。西インド諸島原産です。
西インド諸島やメキシコに自生する多年草で、観賞用の園芸種です。日本には江戸時代の終わり頃(1845年)渡来し、その頃はサフランと、誤って呼ばれていたそうです。ですが明治7年、今の名前に改められたそうです。
背の高さは、25㎝ほどで、花の直径は6㎝ほど、雄しべは6個、そのうち3個は長く3個は短いと資料にはありましたが、写真ではわかりにくいようです。雌しべの先(柱頭と書き、チュウトウと読みます。花粉を受け取るところです)は3っつに割れているのが分かります。同じく写真ではわかりにくいですね。(サフランモドキより一部引用しました)
サフランモドキではないかも知れませんので名前が分かる方は教えて頂けると有り難いです。
*ハブランサスでした。ヒガンバナ科。ハブランサス属。横向きに咲くことで分かるそうです。


「サフランモドキ」はヒガンバナ科。ゼフィランサス属。西インド諸島原産です。
西インド諸島やメキシコに自生する多年草で、観賞用の園芸種です。日本には江戸時代の終わり頃(1845年)渡来し、その頃はサフランと、誤って呼ばれていたそうです。ですが明治7年、今の名前に改められたそうです。
背の高さは、25㎝ほどで、花の直径は6㎝ほど、雄しべは6個、そのうち3個は長く3個は短いと資料にはありましたが、写真ではわかりにくいようです。雌しべの先(柱頭と書き、チュウトウと読みます。花粉を受け取るところです)は3っつに割れているのが分かります。同じく写真ではわかりにくいですね。(サフランモドキより一部引用しました)
サフランモドキではないかも知れませんので名前が分かる方は教えて頂けると有り難いです。
*ハブランサスでした。ヒガンバナ科。ハブランサス属。横向きに咲くことで分かるそうです。


2009年07月18日
時計草(トケイソウ)
散歩中に偶然見つけました。色々な方のブログでは拝見していました。実物を見ることができて良かったです。
「トケイソウ」はトケイソウ科。トケイソウ属。つる性常緑宿根草です。原産地はペルー、ブラジルです。
1730年に渡来とありました。意外と古い花ですね。
時計の形に似た複雑な花で、糸状で平らに開いた副花冠は文字盤に見え、先は青、中ほどは白、基部は紫色を帯びて綺麗です。各花は一日で終わるそうです。秋迄咲きます。
別名:パッションフラワー
パッションフルーツはトケイソウの仲間です。果実はジャムやジュースとして利用されるそうです。


「トケイソウ」はトケイソウ科。トケイソウ属。つる性常緑宿根草です。原産地はペルー、ブラジルです。
1730年に渡来とありました。意外と古い花ですね。
時計の形に似た複雑な花で、糸状で平らに開いた副花冠は文字盤に見え、先は青、中ほどは白、基部は紫色を帯びて綺麗です。各花は一日で終わるそうです。秋迄咲きます。
別名:パッションフラワー
パッションフルーツはトケイソウの仲間です。果実はジャムやジュースとして利用されるそうです。


2009年07月17日
ペトレア
先日母の知人から電話があり、「珍しい花があるので見に来て」とお誘いを受けました。
早速お邪魔すると今まで見たことがなかった花がありました。
早速撮影して家で検索してみました。名前が判明しました。
「ペトレア」はクマツヅラ科。ペトレア(ヤモメカズラ)属。原産地はメキシコ、中南米です。
ペトレア(ヤモメカズラ)属は中南米を中心に約30種がありますが、その中でもヴォルビリスは日本でも鉢植えなどで出回る比較的一般的な種です。
メキシコ、中米に分布する常緑性のつる性低木で、枝は細くてたくさん枝分かれして弓状にしなり枝先に紫色の花を房状に咲かせます。その姿からパープルリースの別名があります。花自体の寿命は長くないですが、花びらが散った後にも星形の淡い青紫色の萼(がく)が残り長期間その美しさを楽しむことができます(この残った萼は果実が飛散するとき、役に立つのだそうです)。
葉の表面がざらざらしており紙ヤスリのようなのでサンドペーパー・バイン(バインは’蔓’の意味)という英名もあります。紫花以外に白花のアルビフロラもあるそうです。
「ヤサシイエンゲイより引用しました」
私が見たのはまさしく白花のアルビフロアだったようです。それにしても不思議な花を見ました。良かったです。見せて下さった方に感謝です。


早速お邪魔すると今まで見たことがなかった花がありました。
早速撮影して家で検索してみました。名前が判明しました。
「ペトレア」はクマツヅラ科。ペトレア(ヤモメカズラ)属。原産地はメキシコ、中南米です。
ペトレア(ヤモメカズラ)属は中南米を中心に約30種がありますが、その中でもヴォルビリスは日本でも鉢植えなどで出回る比較的一般的な種です。
メキシコ、中米に分布する常緑性のつる性低木で、枝は細くてたくさん枝分かれして弓状にしなり枝先に紫色の花を房状に咲かせます。その姿からパープルリースの別名があります。花自体の寿命は長くないですが、花びらが散った後にも星形の淡い青紫色の萼(がく)が残り長期間その美しさを楽しむことができます(この残った萼は果実が飛散するとき、役に立つのだそうです)。
葉の表面がざらざらしており紙ヤスリのようなのでサンドペーパー・バイン(バインは’蔓’の意味)という英名もあります。紫花以外に白花のアルビフロラもあるそうです。
「ヤサシイエンゲイより引用しました」
私が見たのはまさしく白花のアルビフロアだったようです。それにしても不思議な花を見ました。良かったです。見せて下さった方に感謝です。


2009年07月16日
キンケイギク
我が家の花です。時期的には盛りを過ぎています。
「キンケイギク」はキク科。コレオプシス(ハルシャ)属。原産地は北アメリカ(アメリカ南部)です。美しい花の色、姿、大きさなどから「金鶏(きんけい:体の黄色い鳥)」を想像して命名されたようです。
「金鶏菊」は花の中央部まわりに紫色の模様があるが、「大金鶏菊(おおきんけいぎく)」にはそれがないそうです。
我が家のは「オオキンケイギク」のようです。母が買ってきたものです。花期は6月~7月とわりと短い花です。終わり間近で痛みが目立ちます。残念です。


「キンケイギク」はキク科。コレオプシス(ハルシャ)属。原産地は北アメリカ(アメリカ南部)です。美しい花の色、姿、大きさなどから「金鶏(きんけい:体の黄色い鳥)」を想像して命名されたようです。
「金鶏菊」は花の中央部まわりに紫色の模様があるが、「大金鶏菊(おおきんけいぎく)」にはそれがないそうです。
我が家のは「オオキンケイギク」のようです。母が買ってきたものです。花期は6月~7月とわりと短い花です。終わり間近で痛みが目立ちます。残念です。


2009年07月15日
グラジオラス
近所の花壇で見ました。オレンジは離れた場所にあったので小さくしか撮れませんでした。
「グラジオラス」はアヤメ科。グラジオラス属。原産地は南アフリカです。その他地中海沿岸、小アジアです。
草丈が70cm~1mになる大型の球根植物です。現在栽培されている園芸品種は1000種類を超えます。春に球根を植え付けると夏に花を咲かせるタイプのものがポピュラーですが秋に球根を植えると春に咲くものもあります。


「グラジオラス」はアヤメ科。グラジオラス属。原産地は南アフリカです。その他地中海沿岸、小アジアです。
草丈が70cm~1mになる大型の球根植物です。現在栽培されている園芸品種は1000種類を超えます。春に球根を植え付けると夏に花を咲かせるタイプのものがポピュラーですが秋に球根を植えると春に咲くものもあります。


2009年07月14日
アガパンサス
100記事を超えました。これからもお花を紹介していきます。宜しくお願いします。
私が通院している病院近くの薬局でみました。雨に濡れた方は我が家の花です。
「アガパンサス」はユリ科。アガパンサス属。原産地は南アフリカです。
明治時代中期に渡来しているようです。
別名は「ムラサキクンシラン」ですが、実際のクンシランとは何のつながりもないです(クンシランはヒガンバナ科)。花の付き方などが似ているので、そのような名前がついたのでしょう。
庭に植えっぱなしでもよく育ち、6から7月の梅雨時期から明けくらいに花を咲かせます。けっこう大型の植物で、花が咲く頃の草丈は70から90センチくらいに達します。花の色は、ブルーかホワイトの品種が多く、よく出回っています。
(ヤサシイエンゲイより一部引用しました)
花言葉:知的な装い
山の斜面などで見かけますが、地面に根を張るので良いようです。


私が通院している病院近くの薬局でみました。雨に濡れた方は我が家の花です。
「アガパンサス」はユリ科。アガパンサス属。原産地は南アフリカです。
明治時代中期に渡来しているようです。
別名は「ムラサキクンシラン」ですが、実際のクンシランとは何のつながりもないです(クンシランはヒガンバナ科)。花の付き方などが似ているので、そのような名前がついたのでしょう。
庭に植えっぱなしでもよく育ち、6から7月の梅雨時期から明けくらいに花を咲かせます。けっこう大型の植物で、花が咲く頃の草丈は70から90センチくらいに達します。花の色は、ブルーかホワイトの品種が多く、よく出回っています。
(ヤサシイエンゲイより一部引用しました)
花言葉:知的な装い
山の斜面などで見かけますが、地面に根を張るので良いようです。


2009年07月13日
ブーゲンビレア
我が家の花です。
「ブーゲンビレア」はオシロイバナ科。ブーゲンビレア(イカダカズラ)属。原産地は熱帯、亜熱帯(南米が主)です。
別名「イカダカズラ」とも呼びます。大輪種~小輪種まで様々な品種があります。紅紫色の品種を主として、ピンク、オレンジ、白などカラフルなバリエーションがあります。枝が細く、支柱などがないとたれさがってしまいます。
花に見えるのは苞(ほう)で、3個の苞(ほう)が集まって1個の花のように見えます。
花言葉:あなたは魅力に満ちている



「ブーゲンビレア」はオシロイバナ科。ブーゲンビレア(イカダカズラ)属。原産地は熱帯、亜熱帯(南米が主)です。
別名「イカダカズラ」とも呼びます。大輪種~小輪種まで様々な品種があります。紅紫色の品種を主として、ピンク、オレンジ、白などカラフルなバリエーションがあります。枝が細く、支柱などがないとたれさがってしまいます。
花に見えるのは苞(ほう)で、3個の苞(ほう)が集まって1個の花のように見えます。
花言葉:あなたは魅力に満ちている



2009年07月12日
トレニア
大分市の佐野植物公園内でみました。
「トレニア」はゴマノハグサ科。トレニア属。原産地は東南アジア、アフリカです。
東南アジア、アフリカに40種ほどが分布する一年草、もしくは多年草です。トレニアという名前はスェーデンの牧師の名にちなみます。花付きの良さと育てやすさ、暑さに強いなどの利点から夏の草花として花壇、鉢、コンテナ植え、寄せ植えなど幅広い用途で広く普及しています。
一般にトレニアの名前で栽培されているのはインドシナ原産の「トレニア フルニエリ」とその変種や園芸品種で 草丈20cm~30cmでよく枝分かれしてこんもりと茂ります。花付きは非常に良く初夏~秋にかけてスミレに似たユニークな形をした3cmほどの花を次々と咲かせます。ハナウリクサ、ムラサキミゾホウズキという別名があります。花色は濃い紫色のものが基本で白、紫、ピンク、赤などカラフルな色彩が揃っており、代表的な園芸品種に「クラウン」「パンダ」などがあります。 めしべの先端が2つに割れており、そこに触れるとぴたりと閉じるおもしろい性質があります。
(ヤサシイエンゲイより引用しました)
まだ試してみたことはないです。今度やってみたいと思います。



「トレニア」はゴマノハグサ科。トレニア属。原産地は東南アジア、アフリカです。
東南アジア、アフリカに40種ほどが分布する一年草、もしくは多年草です。トレニアという名前はスェーデンの牧師の名にちなみます。花付きの良さと育てやすさ、暑さに強いなどの利点から夏の草花として花壇、鉢、コンテナ植え、寄せ植えなど幅広い用途で広く普及しています。
一般にトレニアの名前で栽培されているのはインドシナ原産の「トレニア フルニエリ」とその変種や園芸品種で 草丈20cm~30cmでよく枝分かれしてこんもりと茂ります。花付きは非常に良く初夏~秋にかけてスミレに似たユニークな形をした3cmほどの花を次々と咲かせます。ハナウリクサ、ムラサキミゾホウズキという別名があります。花色は濃い紫色のものが基本で白、紫、ピンク、赤などカラフルな色彩が揃っており、代表的な園芸品種に「クラウン」「パンダ」などがあります。 めしべの先端が2つに割れており、そこに触れるとぴたりと閉じるおもしろい性質があります。
(ヤサシイエンゲイより引用しました)
まだ試してみたことはないです。今度やってみたいと思います。